こんにちは、ギター/ボーカル講師のAngler Ogiです。
皆さんは「歌がうまい人」と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
「歌がうまい」には多くの要素がありますが、それらを挙げてみようとすると意外と漠然としている事に気づかされます。
また、
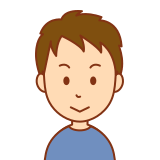
歌がうまくなりたいんだけど、具体的に何をどうすればいいの?
というケースをよく耳にします。
そこで今回は、プロボーカル講師である私Ogi目線で、歌がうまいとはどういうことなのか?について分析していきたいと思います。
↓【今回の記事はこんな内容です!】↓
- 歌がうまいとは、そもそもどういうことなのか。どんな特徴があるのかを解説!
- 実際に歌がうまいアーティストは誰なのかを独自考察!
- 「ボーカルがうまい人」=カラオケもうまいの?という長年のギモンにお応えします!
- ボーカルが上手くなれば、コーラスも出来るのか?という点に着目!
このようなことに疑問を持っておられる方のお役に立てれば嬉しいです!
〇歌はどんな要素で判断されるのか?
好きなアーティストというのは、人それぞれ違います。
しかし、 音楽好きの方に (好き嫌いは別として) 歌が上手い人は誰?と訊いてみると、意外と共通したアーティストが挙がる事が多いのです。
では、その要素を細かく挙げてみましょう。
- 自分の音域を正確に把握した上で、ピッチ(音程)が正確
- リズムが安定していて、アカペラ(ソロ)で訊いてもグルーヴがある
- 自分の声の特徴をしっかりと理解している
- 発声方法が的確 (曲にマッチしている)
- 声量があり(ブレス(呼吸)や響き含む)、そのコントロールが的確
- 歌詞の意味をしっかりと理解し、抑揚をつけて世界観を表現できている
- 歌い方に個性がある
私Ogiが考える要素は、この7つ。主にピッチ、リズム、発声、抑揚+個性となります。
そもそも、音楽には 音楽の三大要素というものが存在します。それが以下の3つ。
- メロディ
- リズム
- ハーモニー(和音)
このうちボーカルが担当できるのは、メロディとリズム。
そこに人間の声という要素がプラスアルファで加わり、抑揚と個性で色付けされていきます。
では、7つの要素を1つずつ分解してみていきましょう。
要素①音域とピッチ(音程)の正確さについて
音楽の三大要素の1つ、メロディ。
それを声で表現するのがボーカルである以上、ピッチの正確さというのは必要不可欠な要素です。
実際、上手い人というのは殆どピッチが外れませんし、「音痴=ヘタ」というレッテルを貼られてしまうというケースも多く見受けられます。
しかしここには大きな落とし穴が。ボーカルの体験レッスンに来られる方はほとんどがそうなのですが、
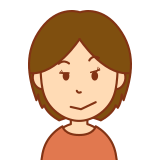
音程が正確なら歌がうまいと言われるはず!絶対に音を外さないように歌わなきゃ!!
このように考え、結果として音域を見誤り、ノドで音程を取って音程ありきで歌ってしまう方が多いのです。
正しい音程の取り方というのは、
- きちんとした呼吸法(腹式呼吸がメイン)を用いる
- 地声と裏声(ミックスボイス含む)をコントロールした上で、ノドは脱力。
- 空気が通るラインを意識しつつ響きをコントロール
- 自分の体内で響く声に意識をおく(聴く)
この4つを意識しながら音程をイメージすることで、結果としてピッチが正確になる、というのが理想です。
音程が合っているからと言って、ノドを閉めて(締めすぎて)出している音はボーカルでは「歌えている」とは言えません。
正しい発声法できちんと出ている音こそ、その人の音域なのです。
歌がうまい人は確かにピッチが正確でコントロールもうまく、楽に高音を出しているイメージがあります。
そのため、歌がうまい人=ピッチが正確&音域が広いという図式は確かに成立します。
ただ、ピッチが正確=全員がうまいという図式は成立しませんので、ご注意を!!
aiko、吉田美和(DREAMS COME TRUE)、MISIA、岡野昭仁(ポルノグラフィティ)
Taka(ONE OK ROCK )、稲葉浩志(B’z)、越智志帆(Superfly)
要素②リズムの正確さとグルーヴについて
音楽の三大要素の1つ、リズム。これは当然ボーカルにも当てはまります。
ボーカルのリズムというと歌詞のリズムに目が行きがちですが、実はブレスをリズミカルに入れるというのも、非常に大切なこと。
ブレスも歌詞の一部だと考え、8分音符や16分音符、時に3連符のような感覚でブレスをコントロールできれば、歌い方は一気に変わります。
勿論、歌詞のリズムの割り振りを正確に取るのも大事ですし、身体で感じる音楽的なノリ(グルーヴ)とマッチさせていくことで、ドライブ感(臨場感)のある歌い方が出来るようになります。
稲葉浩志(B’z)、川畑要(Chemistry)、矢沢永吉
要素③声の特徴について
クセのある歌い方については賛否両論ではありますが、やはり声質が特徴的な人(同じ系統のアーティストがいない人、よくモノマネされている人)の歌い方は非常に魅力的です。
低音が強く響く声なのか、それとも高音がどこまでも伸びていくのか、ハスキーボイスなのか。
こういった、個人特有の特徴を生かせる歌い方や曲を選ぶと、何も考えずに曲をチョイスした時よりも上手く聞こえるようにまります。
ボーカル講師として、私が生徒様に曲を提案する際、最も大事にしたいのがこの部分。生徒様からは、
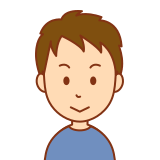
このアーティストの曲、歌えると思っていませんでした!トライしてみたら、周りの評判が良くてびっくりしました!
といったお話もよくあがります。
自分の声質と対極にあるアーティストの曲を歌ってみたらハマった!なんていう事も多くある為、声質というのは非常に奥が深いのです。
桜井和寿(Mr.Children)、桑田佳祐(サザンオールスターズ)、草野マサムネ(スピッツ)
要素④発声方法について
声の出し方というのは、元(基)をたどれば一つのルートしかありません。それは、
〇吸った息を吐く→声帯に空気が当たり、声帯が震える→体に響き、声になる
こういったシンプルなものです。ただ、声帯を自分自身でしっかりとコントロールすることが出来れば、人間は実に様々な声を出すことが出来るのです。
オーソドックスな声の分け方としては、地声と裏声に分ける考え方が一般的です。
そこからさらに複数の声を使い分けていきますが、有名なのはファルセット、ヘッドボイス、ミックスボイス(全て裏声の一種) でしょうか。
- ファルセット・・・ハスキー気味な声質で、空気が漏れる声質。高音が出るが声量が出にくい。切なげな表現でよく使われる。
- ミックスボイス・・・多くのアーティストが使っている声質。ほぼ地声のような力強い響きで、高音でもパワーが出る反面、コントロールを誤るとノドを痛めやすい。
- ヘッドボイス・・・ツヤのある高音が出るが、「裏声」っぽさはしっかりと残ったまま出る。芯が強く太く出る為、よく利用される。(ハードロックやオペラ等の声もこれを昇華させたもの)
これらの声質をバランスよく使用しつつ、曲の表情に合わせて使い分けが出来るアーティストの歌は、実に味わい深く引き込まれるような魅力があります。
ATSUSHI(EXILE)、堂珍義邦(Chemistry)、HYDE(L’arc~en~Ciel)、水樹奈々
要素⑤声量(響き&ブレス含む)のコントロールについて
歌を歌う上で無くてはならない要素として、よく挙げられるのが声量です。
声が小さいと何を歌っているかわかりませんし、地の声量がすごい方ほど、コントロールも綿密に行っているケースが多いのです。
元の声の音量に、声の響く場所をコントロールすることで、声×響きの図式が出来上がり、鼻腔・口腔・咽頭腔(ノドの奥の空間)の3点で掛け算のように倍増できるのです。
その為にはしっかりと息を吐いてから吸う、という呼吸の基礎をしっかり固めておき、必要な時に必要な分だけ呼気を使う、という事も必須。 肺活量とそのコントロールも重要になってきます。
声量はこのように響き/呼吸と密接な関係がありますが、そもそもの声の音量を上げる方法として、
- 身体そのものの使い方
- 腹部やノド周辺の筋肉量
- 体幹の強さ
これらも関係がある為、トレーニング次第である程度改善する事も出来ます。
西川貴教(T.M.Revolution)、岡野昭仁(ポルノグラフィティ)、越智志帆(Superfly)
要素⑥歌詞の世界観と表現力
ボーカルを語る上で欠かせないものと言えば、歌詞を挙げる人も少なくありません。
楽器を演奏しながら歌う事を「弾き語り」というように、そもそも歌とは、自分の思いや考え方・感情等をメロディに乗せて叫んだのが起源であると言われています。
その為、聴いてくれる人たちをいかに「自分の歌詞の世界観」に引き込めるかどうか、というのが、ボーカリストとしての1つの指標となります。
そういった意味では、自身で作詞(出来れば作曲も)が出来ると強いですね。
秦基博、藤原基央(BUMP OF CHICKEN)、安室奈美恵、米津玄師
要素⑦歌い方の個性
こちらも一歩間違えればクセが強いという表現になりますが、本当にうまいボーカリストは、間違くなく特徴的な歌い方や、特有の発声方法、声のコントロール法を持っています。
誰にもマネが出来ない歌い方(マネをする方は絶え間なく存在する)を持っている方は、まさしく歌のカリスマ。
その為、私がボーカルレッスンの指導に置いて、最も尊重したいと考えているのがこの「個性」です。
この個性という物は持って生まれた部分や育った環境なども大きく影響している為、才能の一つであることに間違いありません。
ただその才能を生かしていく為の努力、輝く場を得るための行動力など、様々な歯車がかみ合ったときに発揮されるものです。
ある意味、ボーカリストとして最も大切な部分かもしれません。
宇多田ヒカル、小田和正(オフコース)、稲葉浩志(B’z)
〇ボーカルがうまいと、カラオケもうまいの??
こちらは少々複雑です。そもそもカラオケでうまいと言われる歌い方は、どのようなものなのかという事を考える必要があります。
まず、純粋に歌がうまい人のカラオケ=うまい、これは変わらない事実です。
ただ、「歌がうまい人はカラオケで必ず高得点が出せるというわけではないのです。
カラオケの採点マシンの基準という物は機械的に組み上げられて作られたもので、
- 音程の正確さ
- リズムが合っているかどうか
- ノド声になっていないか(腹式呼吸が使えているかどうか)
- マイクできちんと声が拾えているかどうか
- 歌詞を間違えていないか
- しゃくり(下から音程をすくい上げるような発声)が無いか
- ビブラートがかかっているか(人工的にかけたものでもOK)
- 響きは真ん中あたりで安定しているか(ミックスボイスだと高得点)
このような基準を基に採点されます。実際に見てみましょう。
カラオケで高得点を狙うなら
音程とリズムについては、カラオケの画面に表示されるバーと、いかにピッタリ合っているかという所に基準が置かれている為、多少であればノドで音程を取っていても点数は落ちないのです。
また、ノド声でないミックスボイスで、口から鼻の辺りに響きを集中させるように歌えば、必然的にマイクで声を拾いやすくなるため、簡単に点数は上がります。
歌詞はきちんと覚えておけばクリアできますし、ビブラートは自然にかかるものでなくても構わないようです。
コブシのように「あぁ(↑↓) あぁあぁあぁ 」とリズムに合わせて音程を上下させれば、ほとんどの機種で「ビブラート」として判定されます。(苦笑)
あとは任意の音程に対してパチン!と当てに行く意識を持つこと。
お腹をタイトに使い、ブレスがグゥ~↑っと上がる感じが無ければ、しゃくりと判断されません。
この要素が出来ていれば、歌詞に感情がのっていなかったり、グルーヴが無かったり、声に強烈な個性が無くても高得点が出ます。
私の元生徒様には、得意なアーティストの曲なら全て100点をだせるという方も普通にいました(ご自身の歌い方は不満だと仰っていました)。
カラオケで点数が高い=歌がうまい、という図式は成り立ちませんので、ご注意を!
〇ボーカルが上達したらコーラスも出来る?
これはまた別の問題となりますが、「ボーカルが上達するとコーラスもやりやすくなる」という事が言えます。
ボーカリストには、ソロボーカルにしか向かないタイプの声質も多く(良くも悪くもソロとしての個性が強い)、実はコーラスは苦手というプロ歌手も少なくありません。
ですが、コーラスをやる要素として「ボーカリストの要素」の幾つか(ピッチやリズム、発声/ブレスコントロール等)は関わってきますから、やっておいて損はないと言えます。
その「ボーカリスト」としての練習にプラスして、「コーラスをやるための練習」を積み重ねれば、確実にコーラスは出来るようになります。
コーラスのポイントとしては、
- 相手の声を聞きすぎない(和音として声を捉える)
- 自分の声の芯を抜く(ファルセットやヘッドボイスを鍛える)
- ブレス量のコントロールを学ぶ
こういった事が挙げられます。
ボーカル講師によるレッスンでは、多くの講師がコーラスにも対応していますので、ご興味ある方は講師に尋ねてみてくださいね。
〇まとめ
いかがでしたでしょうか。
私Ogiの個人的な見解で、歌のうまい人に共通する特徴、カラオケとボーカルの関係等を纏めてみました。
「じゃあOgiはどのボーカリストがうまい人だと思っているんだ!?」
という事を思う方もおられるかと思うのですが、歌のうまい・ヘタというのは個人の主観・価値観により、どの部分に比重を置くかによって変わってきますので、実は断言できない部分なのです。
皆さま一人ひとりの心の中に「この人が最高!」というアーティストを胸に秘めて、趣味の合う方とは楽しく、趣味の違う方とは認め合いながら、歌の上達を目指してみてくださいね!!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。







コメント